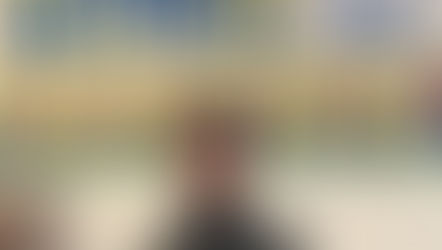【佐渡の現状と未来、市長の役割、包括的な内容】
Q. 現在の佐渡の状況を客観的に表現してください。
A.人口減少と高齢化、それに伴う経済(消費)活動の停滞が暗い影を投げかけています。人口減少は国全体の問題であり、減少は
一定程度、仕方がないと判断すべきですが、人口7万人の時も約年1000人減っていたのが、人口5万4千人の現在も同数減っており、
人口減少が拡大していること。特に64歳以下の子供から働く世代が減っているのが大きな問題です。また、人ひとりによる経済効
果が約120万と言われており、単純に毎年12億円の消費が佐渡から消えていることとなります。一方働く場所が無いと言われていま
すが、医療、介護、観光、建設、建築、農林水産業などいずれも人手不足で、経済活動の停滞の要因です。また、佐渡を歩いて感
じるのが、空き家が多いことや高齢化に伴う集落機能の喪失への不安です。その他福祉、医療、介護なども大きな課題です。早急
に経済を元気にし、U・Iターンなど定住促進と人材確保の徹底を進めると共に、佐渡の豊かさを知る教育や佐渡ならではの文化
、スポーツ、自然などへの体験など総合的な政策を組み合わせ、島民はもちろん、国内外の多くの人が、住みたくなる、訪れたく
なる島作りが必要と考えます。
Q. 市長は佐渡市のトップセールスマン。どのような活動を考えますか?
A.売込みベタというのは昔から佐渡の課題と言われています。高野市政以降、農水省、環境省、国土交通省にいつでも伺い、何で
も相談できる状況でした。国連、東京大学、新潟大学なども様々な課題で協議できる体制でした。大手スーパーや老舗百貨店など
との取引を持つなど、官、学、民それぞれの立場で連携を深めておりました。佐渡の自然、文化、環境、教育、経済それぞれを高
め合うための、首都圏にへばりつく、そして粘り強い情報発信と営業活動が必要と思います。
また、民間企業や市会議員と連携した営業活動による佐渡ワンチームセールスの実施も進めていきたいと考えています。
Q. 過去、佐渡市では中央官庁から総合政策監として受け入れていましたが、現在そのような交流はないようです、
今後の中央とのかかわりはどうされますか?
A.トップセールスとも関連しますが、情報の発信、共有、詳細の取得などに国から派遣される職員は必ず必要です。特に佐渡市に
派遣されていた国土交通省、総務省、関連のある農林水産省の職員は、情報の面だけでなく、政策立案、職員教育、国への適切な
案内など、大きな役割を果たすと考えています。もう一度国からの派遣を、お願いしたいと考えています。
Q. 福祉やインフラ整備などお金のかかる事業に投資するには、相応の財源が必要ですが、どのように獲得しますか。
A.佐渡市の歳出予算額約445億円に、対して税収は約50億円、やはり国、県との連携の中で財源の確保が必要です。私は離島で
ある佐渡の独自性を活かし、日本の10年先の課題を解決するモデルを目指し、佐渡の課題解決と財源の確保が両立可能と考えま
す。離島の特性を活かし自然共生、再生エネルギー、文化、スボーツ、教育、健康寿命対策などを日本の先を行くプロジェクト
として構築していきたいと考えています。また、トップセールスとも絡みますが、設備投資と人材確保により民間企業島外売込
みを促進し、官民合わせて島外から稼ぎ、島内で循環し、島外に出さない循環型成長戦略も必要です。
Q. 施策の実現のためには、佐渡独自に稼ぐ力が必要ですが、具体策はありますか。
A.
Q. 世界遺産登録に対してはどのように取り組みますか。
A.世界遺産登録は島外の方の受け入れ体制の整備と佐渡市民が誇りを持ち、佐渡を守り続けていく体制を作るという2つの視点
が必要となります。既に対応が遅れていると感じていますが、ホテル、旅館、民宿、ゲストハウス、民泊等多様な宿泊施設の整
備、ガイドの育成、佐渡の豊かな農林漁業産品の提供体制、バリアフリー化、フリーWiFi整備など、お客様がリピーターとなる
佐渡ならではのおもてなしの体制づくりが急がれると思います。一方市民が世界遺産の島を継承するためには、佐渡を知るキャ
リア教育、景観整備、イベント等の実施、観光と連携した資金循環の仕組み作りが必要と考えております。
Q. 農村集落の整備、耕作放棄地、それに伴う限界集落化への対策は?
A.農村集落の整備については、集落自体のコミニュティ(共同体制:各組合等や祭り、助け合いの協業体制)や農業の担い
手の育成に加えて、中山間地域は集落営農の仕組み作りと消費者との交流や受け入れ、平野部は職場となる農業を作って
いくという仕組み作りが大事だと考えます。集落で農業をどうしていくか、集落の人と県、市、JAが一緒に知恵を出し
考えていく体制を作り、地域にあった担い手を育成していく。その中に将来の農地の管理方法を検し、守るべき農地と放
棄する農地を明確にしていくべきと考えています。
限界集落とは子供の数とか、高齢者の数で決められるものであることから、単に限界集落という概念ではなく、集落ごと
にそれぞれの課題を話し合い、集落としての動き、大学等交流人口の受け入れなど話し合うことから始めるべきと考えて
います。
【産業育成】
Q. 第一次産業、第二次産業、第三次産業の連携スキームをお聞かせください。
A.まず考えるべきは各産業、各業種ともそれぞれの課題があり、特にコスト、流通量、流通方法などの面から、連携が進んで
いないのが現状です。私は、販売戦略からの6次産業化、農商工連携を進めて行くことが重要と考えます。官民合わせたセールス
の中で首都圏に販売しながら、需要に合わせた商品を供給する。販路の中で新たな商品を開発する仕組みにより、企業の参画を
促していきたいと考えています。特に観光との連携はホテルへの安定供給の体制作りが不足していると感じています。農林漁業
者などとのマッチングが必要ですし、ホテルのオリジナルお土産等による連携も進めていく必要があります。また逆に、販売戦
略さえあれば他業種からの第一次産業参入は可能と考えています。米、畜産など企業参入かしやすい環境の整備が必要です。
Q. 島外に向けての佐渡産品拡大の手法はどのような施策ををお持ちですか。
A.担い手の育成や他の項目でご説明したとおり、農林水産品に限らず、観光、工業製品、文化などを首都圏を中心にし
た販売戦略とセールス活動につなげ、情報発信、高付加価値及び多様な販売網の確保を作る必要があります。そのため
の市長自らのトップセールスの体制を市、関係機関と連携し、積極的に取り組む必要があると考えます。
また、民間企業と市が連携した、販売、流通を、首都圏と佐渡を繋ぐ、チームの設立も必要であり、小規模から中規模
程度の直売体制の構築も必要であると考えています。
国の交付金を活用し、一層の輸送コストの低廉化にも取り組まなければなりません。
【農林水産業(第一次産業)】
Q. 農林水産業の担い手育成にどう取り組みますか。
A.農業の担い手は佐渡一律ではなく、地域の営農形態にあった経営体を育成すべきと考えております。中山間地域は集落
営農、果樹、野菜等を中心とした複合経営、平野部は米の大規模経営、米に果樹、野菜等を加えた複合経営などを1つの
モデルと考え、経営支援と技術支援により育成すべきと考えています。
漁業の担い手育成は漁協、定置組合等の担い手の確保、国、県の制度を活用した支援、浜の賑わいを取り戻す小規模、兼
業漁師の育成等が必要であります。
林業については、佐渡の自然再生の源を担う事業です。佐渡産材の活用方針を示しながら、各組合の健全経営を目指し、
佐渡産材の生産コスト削減計画と公共施設等への利用計画なども策定しながら、経営体の育成を図ることが、林業の活性
化や雇用の面で重要と考えます。
農林水産業とも販売戦略とセットで担い手育成を進めることが必須であると考えています。
Q. 2月20日の日報佐渡版に、トキ認証米の事例を他の農産品に波及させ、ブランド化促進という政策が書かれていまし
たが、現在ほ場整備地区には総面積の20%の園芸導入が義務づけられています。ある程度の収入が見込めるためには、
ブランド化が必要と考えますが、具体的にどのようにやっていくのか教えてください。
A.いくつかの方針を組み合わせることが必要だと思います。まず20%の園芸導入は画餅であり、本来その政策導入時に市として
明確に反対しなければなりません。1ヘクタールの園芸はどんなに大変か、所詮県の机のうえで書いた餅に過ぎません。私は県
に地域要件、市場規模要件、土質要件を入れることを要望します。
基本的な対策としては、
園芸作物は市場が近くになければ成り立ちません。まずは佐渡、新潟、首都圏の順で販路を考え、施設園芸か果樹、路地なら
ば枝豆などの佐渡でないものを作る必要があります。ル レクチェ、ビオレなども検討する必要があります。また、団地化、園
芸の組織化も図り、個々の農家にやらせないことも必要になると思います。需要のあるいいものを作れば売れます。誰がどこ
で何を作るか、技術をどどのように高めるのかそれが販売戦略だと思います。しっかりと皆で議論し、進めましょう。
【工業(二次産業)】
Q. ご質問をお待ちしております。
A.
【商業・観光・サービス業(三次産業)】
Q. 観光誘客対策は非常に重要と考えますが、具体的な方法をお聞かせください。
A.佐渡にお出で頂くには、もう一度行きたい、ゆっくりと回りたい、体験してみたい、異なる空間で過ごしたいなど、佐渡なら
ではを愛して頂けるお客様を増やしていく必要があります。世界遺産の国内推薦は1つのチャンスであり、これをどのように活
かすが今後の佐渡観光に大きな影響があるものと考えます。コロナウィルスの影響からしばらくは厳しいかもしれませんが、こ
んな時こそ、情報発信と受け入れ体制の整備を、進めなければなりません。多様な宿泊施設の整備として、ホテル、旅館、民宿、
ゲストハウス、民泊、宿坊などで佐渡を、感じることができる宿泊の提供や、観光施設のコンテンツの磨き上げ、体験などの充
実と予約などの利便性の向上、文化ツーリズム、スポーツツーリズム、トキ環境再生ツーリズムなど佐渡の豊かさを活かした誘
客に取り組むべきと考えています。
【生活・環境】
【子育て・若者支援】
Q. 佐渡は地産地消条例を制定していますが、学校給食・施設給食などの取り組みはどのようにしますか。
A.佐渡の地産地消の推進については野菜、果物などを長い期間、生産、保存し供給する仕組み作りが大事です。例えばトマト
を食べたくても、佐渡産は一定の季節しか収穫できませんから、施設園芸での生産が必要となります。この施設園芸で若手農
家が収入を得ることができるような仕組みを併せて作ることが大事だと考えています。魚については、加工等により、供給量
を、増やしていかなければなりません。市場、農協、漁協と連携し、何がいつ必要で、他産地と代替できるものは何で、量は
どのくらいか。などを基礎にした生産計画を作り、新しく生産者を育成し価格を支える仕組みと併せて推進する必要があると
考えています。学校給食については現段階では給食センターへの供給と利用の対策が必要です。児童、生徒の成長のための多
様な種類と安全な食の提供が必要となります。需要に合わした生産計画を立て、価格を買い支える仕組みと併せて推進する必
要があります。教育委員会の判断が大きいですが、私自身は現段階での業務委託には反対です!
Q. 若者の島外流出が止まりません、島外流出を止める手立ては。
A.大学がないからとも言われていますが、大学があっても雇用がなければ、流出時期が延びるだけです。雇用を生み出すに
は、幅広い産業で働きやすい環境を整備すべきです。農林水産業は担い手として技術と所得を確保できる支援制度。観光産
業、建設業などは職場環境の専門職の育成や確保などにより、帰って来やすい環境を作る必要があります。また、私の私見
ではありますが、集落コミニュティがあり、祭りや地域活動の元気な農漁村集落には、若者がいるのではないかと考えます。
また、農業が元気であれば、担い手が出来ることは西三川地区の農家さんたちが証明してくれています。
企業誘致としてIT関係の企業は離島のハンディは少なく、人材の育成を官民併せてできるのではないかと考えます。
空き家対策と組み合わせ、様々な角度からの対策が必要です。島の賑やかを作るためには、大学のキャンパスが必要です。佐
渡市と連携している大学の、サテライトキャンパスの佐渡設置に向けて働きかけて行きます。
Q. 若年者の将来に向けて、未来が描けるビジョンをお聞かせください。
A.佐渡に住む豊かさや安心安全な暮らしが単なる経済ではなく、自然との共生の中での、子育てや家族との多くの時間、文化、
スポーツ、祭りなどを常に楽しむ環境など、佐渡ならではの人生設計を若者に提案していくべきと考えています。しかしなが
ら、高齢化社会、人口減少社会に立ち向かうため佐渡全体の将来ビジョンの作成と併せて、多数の市民、企業、大学などの参
画を頂き、多くの知恵により作成すべきと考えます。
Q. 子供を育てる環境で有効な手立てはなんですか。
A.子供を、育てる環境は年代ごとに幅が広いため、政策のポイントだけ記載させて頂きます。
私自身もできなかったのですが、2歳くらいまではご家族と一緒にいることができる環境作りが必要と感じています。そのため
には、育児休業等の取得体制の整備や一定の所得確保が必要となります。そのためには企業と子育て支援に関する意見交換会等
を開催し、育児休業の所得推進について検討したいと思います。また、家庭での育児支援金制度も検討し、家庭での育児を、支
援するべきと考えます。
併せて、多子世帯への支援金の設立が必要と思っています。これは3子目以降のお子様に対して、成長のステージに併せた支援
を考えています。300万円を上限として交付していきたいと考えています。
また、雨の日の遊び場がないというご意見も多く頂いています。公共施設の活用も含めて、検討しなければならないと思います。
その他多くのポイントがあり、病院の体制、病児保育、公園(子供の遊ぶ)、育児相談の体制、離島のメリットとハンディ、子育
て世代の働き方などあります。保護者の皆様と定期的な話合いの場を作り、子育て世代の意見を政策に反映すべきと考えます。
【高齢福祉】
Q. 高齢者の状況把握を効率的に行う手法を構築すべきと思いますが。
A.高齢者の見守りサービスは様々な対策が進められています。郵便局やヤマト運輸さんなどとの連携も一つですが、今後はセン
サーやテレビなどを活用した見守りなどの対策が必要と考えています。IT企業や大学との連携など様々な角度から検討を進めます。
Q. 生活・買い物弱者などが社会問題となっていますが、どのような対策がありますか。
A.高齢化と人口減少の組み合わせにより、高齢者の免許返納が今後増加することに加え、地域のちいさなお店がなくなっていま
す。市と民間企業、ボランティアなどで高齢者支援隊などを組織し、生活支援をすることも必要と考えます。また、交通手段と
してのコミニュティタクシー、現在民間企業が行ってい移動販売車の充実、スマホ等に対応できる方向けの買い物代行など様々
な手段を組み合わせて行く必要があります。
【インフラ・交通空港整備】
Q. 老朽化した公共インフラ対策のプランはお持ちですか。
A.佐渡全体の公共インフラデザインを市民と協議し、将来像を作る必要があります。支所、サービスセンターで地域将来像を検討
する中で、市民の皆様と議論していきます。しかし、一つ一つの施設に維持管理コストがかかるのも現実ですので、耐用年数、利
用率、代替施設の有無などの市民サービスへの効果も検討していく必要があります。
Q. 高齢者や子育て世代が移動しやすい環境整備が必要だと思いますが、どのような対策がありますか。
A.実は私自身が今足の怪我で松葉杖となっており、福祉、インフラ整備の両面からバリアフリー化に向けての積極的な対策の必要
性を改めて感じています。財源の確保については福祉、介護、医療などは基本的には国の政策に合わせて行いますが、佐渡市独自
事業については、事業効果を見据え、最大の効果を、最小の経費で行なうことを徹底します。
インフラ整備についても、国の制度の活用を基本に効果対費用をしっかりと図り、無駄な事業、無駄なコストを徹底して見直
し、必要なものを最低のコストで整備するよう取り組みます。国、県としっかりと連携し、財源の確保に努めます。
Q. 道路整備、佐渡空港整備について、どのように進めますか。
A.国道、県道については、県と連携を図り、防災対策の面から改修の必要性等を、調査し、要望していかなければならないと考え
ています。また、市道等についても、欠かせない生活道路であったり、消防車等が入りにくい道路であったり、大きく傷んでいて
も補修がされていないなどがあります。防災という観点から必用に応じた整備を進めます。
空港については、単なる観光ではなく、LCCや裕福層をターゲットとした小型飛行機などの来航などに広がるとともに、農林
水産物、工業製品などの物流の改善に繋がり、佐渡産品の競争力が向上します。また、企業誘致、防災対策としても必要です。
確かに整備までには、多くの時間がかかるかもしれませんが整備さえ決まれば、そこに投資が生まれ企業が動き人が動きます。
いろいろなものが動き出すことが賑やかな島作りの一歩であり、その先に人口減少を止める世界が広がっていると思います。
Q. 佐渡の玄関口である両津港を整備し、人が集い経済活動が活性する場所として機能させるなどは有効と思われます。
A.両津港は佐渡の玄関口であり佐渡の顔でもあります。佐渡に入った時にドキドキ、ワクワクするような玄関口になるような整
備が必要考えています。短期的には駐車場問題や港周辺で滞在できる環境作りが必要ですし、長期的には、県 が検討を進めてい
る両津港の整備計画と併せて市民全体で知恵を絞る仕組みを作り、賑やかな玄関口整備を進めていくべきと考えています。
Q. 島内では、いまだ和式のトイレが数多くみられる。これを改善するだけでもイメージが良くなると思います。
A.トイレの問題は観光地の重要な課題であると思います。この点については甲斐市政の時から様式化への取り組みを始めてお
り、一定の転換は進んでいると思いますが、今後も計画的に進めていくべき問題と考えます。一方で大きな課題と感じている
のが、公衆トイレです。佐渡を歩いてみましたが、とにかく案内が無いから、地元の人しかわからないトイレになっていると
感じました。今は、レンタカーのお客様も多くトイレに苦慮しているともお伺いしています。滞在型観光に佐渡を変える意味
でも、公共施設の利用やアプリ等での案内、洋式化への整備などを進める必要があると考えます。
Q. 佐渡市の遊休施設をどのように活用しますか。
A.遊休施設の利用は、いくつかの確認すべき条件があります。利用する建物の耐震化ができているか、耐用年数がどのくらい
なのか、建物の現状としても大きなコストが必要なのかというところです。条件整備さえできれば、廃校等人が集まることが
可能な施設については、大学などの拠点、企業の研修場としての利用も考えられます。各施設の有効利用は支所、サービスセ
ンターを中心に地域の方や大学、企業などの知恵を借りながら地域に合う利用方法の検討を進めていく必要があると考えます。
【住まい】
Q. 過疎化や、空き家が想定以上に進んでいますが、どのような対策をお考えですか。
A.過疎化は佐渡の中でも大きく差があります。佐渡の周辺部から中央部への人の動きにより、周辺部の過疎化が進んでいます。
また、佐渡全体でも人口減少が進む訳ですから、二重の理由により周辺部は過疎化しています。それに伴い、空き家が増加して
いる状況です。まずは、合併16年の形を見直し、支所、サービスセンターか中核となり、それぞれの地域の特色を活かした、
地域作りを進めていく体制を作り、地域ににぎやかさを取り戻すきっかけを作ります。また、空き家対策は、官民合わせた空き
家対策プロジェクトにより、集落と連携し、使用可能な空き家の整備を行い、手続き等もしっかりとプロジェクトチームで対応
し、職場案内と子育て等生活環境に居住環境を一体として、移住者に提案する仕組み作りを行なう必要があると考えています。
【移住・定住】
Q. 交流人口を増やす施策を教えてください。
A.交流人口とは佐渡を訪れる人を指します。観光に訪れるお客様はもちろん大学交流、自治体交流、ビジネス、文化、スポー
ツ交流などももちろん含まれます。世界文化遺産、世界農業遺産、ジオパークなどのコンテンツを活かしながら、観光のお客
様を増やしながら、佐渡を見る・学ぶ・教える・体験するなどの交流を拡大していくべきと考えています。
Q. U、I、Jターン者が不安に思うことは、教育と病院だと思いますが、佐渡の教育、医療体制にどう取り
組みますか。
A.厚労省の発表した両津病院の廃止方針は、地域の現状を全く反映していない考え方であり、断固として今の医療体制を守り
続けなければならないものと考えます。佐渡病院を中核とし、両津、相川、羽茂、民間医院の連携体制により、この広い佐渡
における医療体制を守り、産まれ育った地域に暮らし続ける事ができる生活環境を維持しなければなりません。国、県、大学
等と連携し、市、議会、企業、市民が一体となったセールス活動により、医師を始めとした医療人材の確保を進めなければな
らないと考えています。
【都市整備・防災・防犯】
Q. 予見できない震災や天変地異などに対する備えは?また、地域の防犯、防災にはどのような対策が必要ですか。
A.昨今の大雨、大型台風、今冬の記録的な暖冬など、異常気象が続いています。対策としては、防災インフラ(港湾、道路、
公民館等拠点など)の整備と地域防災計画が絵に書いた餅ではなく、市民が状況に合わして対応できる仕組みと高齢化集落
への直接的な支援体制を官民合わせて構築していく必要があります。常日頃から地域を回り、防災体制をチェックする市の
体制も必要と考えています。
【環境】
Q. 佐渡市は2050年にカーボンゼロ宣言をしました。市民が取り組むことが必要と思いますが、そのための
環境政策をお聞きします。
A.現段階では、再生エネルギー、水素利用とも大きな技術革新が必要と考えています。しかしながら、低炭素社会の実現は世
界の環境政策への指針となる取り組みにしていくことと、環境と経済が循環する仕組み作りにより持続可能な取り組みにして
いかなければなりません。まずは、そばにある資源である、木質バイオマスの利用、ソーラーによる給湯システムなど多くの
市民の参画を得る対策を進めながら、国のモデル事業となるような水素、新しいバッテリーシステムへの社会実験を進めてい
くべきと考えます。佐渡市の独りよがりではなく、市民、企業と創意工夫しながら、前に進める必要があります。
Q. 朱鷺が増えすぎているとの声もありますが、それに対してどのように考えますか。
A.朱鷺に関する見方を変えなければなりません。もっと積極的に野生の朱鷺を見て頂く仕組みが重要です。また、今回
の朱鷺の野生復帰の成功は全世界でも類を見ない成功事例でもあります。野生復帰の取り組み自体を1つの環境再生成
功モデルとし、世界中に発信することにより、観光だけではなく、研究、学生、他の朱鷺のいる自治体などとの交流を
含めて、多くの効果が佐渡に表れるものと考えています。
農業被害などは、被害のあった田んぼの米は佐渡のみでブランドとして売るなど、観光向けの販売戦略などでカバーし
ていくことも可能と考えています。
Q. 原発関連問題にはどう対峙しますか。
A.原発の再稼働は反対であり、トキの舞う自然豊かな島を継承していくためにも環境と調和した再生エネルギーの推進などに力
を入れていくべきと考えています。
Q. 世界はSDGsの達成を目標に動き出してます、佐渡での展開はどのように進めますか。
A.SDGsとは国際連合が定める17の持続可能な開発目標です。(ご興味のある方は、こちらから)日本でも国を始め、東京大学や、
大手企業などが目標としており、この目標を意識した事業計画で進んでいます。地方自治体もSDGs都市宣言なども行っており、
日本のモデル自治体となるべき取り組みを目指しており、佐渡市がそこに向かっていく姿勢が見えないのは非常に残念だと思い
ます。内容は難しくはなく、飢餓、貧困、質の高い教育、ジェンダー平等、再生エネルギー、気候変動、生物多様性などの目標
であり、佐渡市は国連や日本社会と寄り添い、SDGs都市としてそれぞれの取り組みを進めていくべきと考えています。
【市役所改革・連携】
【本庁・支所改革】
Q. 窓口業務などのアウトソーシング、スマホなどで行政手続きが完結できるシステム導入などはプランはありますか。
A.窓口サービスは市民サービスの基本であり、高齢化に向けて、利便性の向上が必要です。 郵便局やコンビニなどでの窓口
サービスの一部提供の仕組み作りや戸籍窓口の専門職員の育成を進めながら、休日や夜間に取得できる自動証明書交付機のコ
スト等の検証を進めていきます。なお、窓口サービスのアウトソーシングは、佐渡市内に適当な企業がないこと、業務の振分
けが非常に難しいことから、現段階では適当ではないと考えています。
Q. 行政の担当者は数年で異動が慣例となっていますが、各部署で専門官などの設置は効果的だと思いますか。
A.市役所の業務は非常に幅が広いことから、人事異動の際に市民への業務提供などてご迷惑をおかけしていることは指摘され
ています。業務内容によりますが、外部人材登用で専門の職員を確保する。研修、評価、人事異動の適正化により、専門職の
育成なども仕組みとして作る必要があると感じています。
【情報戦略、発信・連携】
Q. 大学などとの連携が停滞していると思いますが?
A.佐渡市は新潟大学、東京農業大学、東京大学、大正大学など、様々な大学と協定を結んでいます。その他多くの大学の学生
も佐渡で活躍していますがトータルコーディネートができていないことから、大学連携の効果が表れていないと感じます。支
所を中心とした地域作りや政策の提言、効果検証などに大学の教授、学生の力を活かし、新しい視点での地域作りを進めてい
くべきで、拠点として、トキ交流会館、廃校、大きな空き家などを活用し、地域の賑やかさの拠点作りも必要と考えます。
Q. シンガポールが国を挙げて取り組んでいる、デジタルイノベーション戦略「スマートネーション」などは、
佐渡市でも学ぶことが多いと思います。
A.これは、交通、住環境、ビジネスの生産性、健康と高齢化、公共サービスの5つの側面にデジタル技術を取り入れ適切な管理
をしていくもので、人口減少、高齢化社会において、適切な対策を取る上で必要となる技術、サービスです。シンガポールで特
に参考になるのは、人材育成の仕組みで、生涯教育へ支援し、市民の高いスキルの取得を、生涯にわたり取得させていく取り組
みです。また、高齢者の見守り、身体の不自由な方とのコミニュケーションなど大きな役割を果たすものと考えています。
佐渡市は日本の20年先は人口減少、高齢化社会と言われていますので、これを解決する、日本のモデルになるべきでもあります。
地域コミニュティが残る佐渡ならばできると思います。国のモデル自治体になるための、一つの戦略として、IT、AIなどを通し
たスマートアイランドに向けた構想づくりが必要と感じています。
Q. 庁舎問題にはどう取り組みますか。
A.私自身は立候補表明の時から、現庁舎では、防災の面でも一階の市民の皆様からご利用頂く、窓口サービスの点(個別の相談
ができない、市民の皆様のプライバシーが守れない、妊産婦、小さな子供をお連れの窓口が2階)でも、大きな課題があると思っ
ています。異常気象が続く中、早急な対応も、検討しなければならないと考えています。
しかしながら、この4年間市民の間でも大きな議論を巻き起こしてきた案件でもありますので、市長に就任させて頂きましたら、
現庁舎を残す場合の適切なコスト、どのような機能が現庁舎に足りないのか、図書館、福祉センターとの複合型などはどうなの
か、支所、サービスセンターの活用をどうしていくのかなど様々な観点から市民の皆様と議論し、早急に結論を出していくべき
と考えています。
活動報告
最新情報